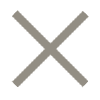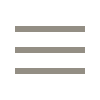ここから本文になります。
相続は被相続人が亡くなったときから始まります。故人を悼む一方で、事務的な手続きを早く進めねばなりません。相続手続きにはさまざまな証明書類が必要なため注意が必要です。
ここでは相続手続きの流れとおおまかなステップについてご説明します。
相続手続きの流れ
被相続人が亡くなり相続が開始されたら、期限までに行わなければならない重要な手続きがいくつかあります。必要な手続きと担当窓口を把握しておきましょう。
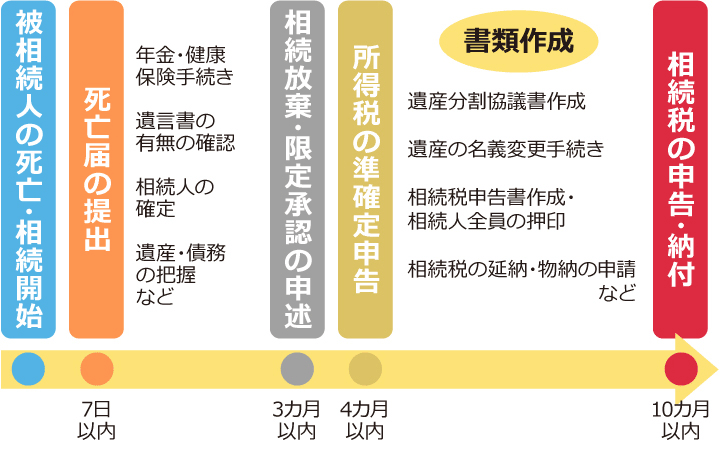
死亡・相続関連手続き一覧と担当窓口
| 被相続人死亡~1カ月くらい (主に死亡関連手続き) |
それ以降 (主に相続関連手続き) |
|
|---|---|---|
| 市区町村役所 |
|
|
| 年金事務所 |
|
- |
| 公証役場 | - |
|
| 家庭裁判所 | - |
|
| 税務署 | - |
|
| 登記所 | - |
|
| 金融機関 |
|
|
| その他 |
|
- |
死亡届について
被相続人が亡くなった場合、死亡した日の翌日から数えて7日以内に、医師の「死亡診断書」とともに死亡届を市区町村役所に提出しなくてはなりません。実際には、亡くなった人を火葬にするのに必要な「死体火葬許可証」を交付してもらうために、亡くなった直後に死亡届を提出しているケースがほとんどです。
金融機関への届け出について
被相続人が口座をもっている銀行や証券会社などの金融機関に口座名義人の死亡を連絡します。通常死亡の連絡は電話でも可能です。死亡の連絡を受けた金融機関は口座名義人の口座を相続手続きが終わるまで凍結します。口座の凍結は口座名義人の財産を保護し、しかるべき相続人に引き渡すためです。金融機関は相続に必要な手続きを案内してくれるので、相続人は案内にしたがって必要書類などを準備し提出することになります。
なお、当社では相続手続きが必要になったお客さま向けに、小冊子『相続手続のご案内』をご用意しています。お取引店舗までお申し付けください。
遺言書の有無を確認
遺言書の有無により、相続手続きは大きく変わってきます。
遺言書には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」の場合は家庭裁判所に提出し検認手続きを受けなければなりません。一方、「公正証書遺言」の場合は検認手続きを受けずに遺言通りに相続手続きを進めることができます。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の配分について話し合い(遺産分割協議)をし、相続人全員が合意した内容を文書にして相続手続きを行うことになります。
遺言公正証書作成件数(全国)の推移
| 2005年 | 69,831件 |
| 2006年 | 72,235件 |
| 2007年 | 74,160件 |
| 2008年 | 76,436件 |
| 2009年 | 77,878件 |
| 2010年 | 81,984件 |
| 2011年 | 78,754件 |
| 2012年 | 88,156件 |
| 2013年 | 96,020件 |
| 2014年 | 104,490件 |
相続人の確定
相続手続きの際に必要になる作業のひとつに相続人の確定があります。文字通り「誰が相続人なのか」を確定し、「遺産分割協議」の当事者が誰かを判断するためです。相続人の調査・確定には、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍類(戸籍・除籍・改正原戸籍など)が必要になります。戸籍に書かれた内容を確認し、誰が相続人に該当するかを判断していきます。
遺産と負債を特定
相続手続きで苦労をするのが遺産(プラスの財産)と負債(マイナスの財産)を特定することです。相続財産の全体を把握することによって、相続放棄や限定承認をすべきかどうかを判断する材料になります。なお、相続放棄や限定承認の手続きは「相続開始後3カ月以内」に行う必要があるため、できるだけ早く財産を特定するようにしましょう。
相続放棄・限定承認・単純承認について
相続には、被相続人の財産をすべて引き継ぐ「単純承認」のほかに、財産を一切相続しない「相続放棄」、条件付き相続の「限定承認」の3つの相続方法があります。
| 相続放棄 | 限定承認 | 単純承認 | |
|---|---|---|---|
| 相続の効果 |
|
プラスの財産とマイナスの財産を相殺し、プラスになった場合のみ相続し、相続人全員で分割 | プラスの財産もマイナスの財産もそのまま相続 |
| 手続き | 家庭裁判所に必要書類を提出 | 家庭裁判所に必要書類を提出 | 不要 |
| 申述人 | 各相続人(単独で手続き可) | 相続人全員(単独で手続き不可) | - |
| 申述期限 | 相続開始から3カ月以内 | 相続開始から3カ月以内 | - |
| 備考 |
|
|
|
遺産分割協議について
相続人が複数いる場合に、誰がどの財産を相続するのかについて話し合うことを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議は相続人全員で行い、全員の同意を得ることが必要です。万が一、当事者間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用することも検討しましょう。
遺産分割協議で「誰がどの財産をいくら相続するのか」について同意した内容は必ず「遺産分割協議書」という書面にし、相続人全員が署名・捺印します。「遺産分割協議書」は財産の名義変更や相続税の申告の際に必要になるため、わかりやすく書きましょう。
準確定申告について
「準確定申告」とは、年の途中で亡くなった被相続人に代わって、相続人が被相続人の所得の確定申告を行うことです。相続人が2人以上いる場合は、準確定申告の書類に連署することになります。準確定申告の計算期間はその年の1月1日から被相続人の死亡した日までです。被相続人に申告すべき所得や控除などがない場合は必要ありません。なお、準確定申告の期限は「相続開始後4カ月以内」です。
相続税申告について
相続税申告は「相続開始後10カ月以内」に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に行わなければなりません。申告期限の日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌営業日が申告期限になります。
正味の遺産額(相続税の課税価格)が「遺産に係る基礎控除額」(=3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下の場合は、相続税が課されないため申告は不要です。ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用して相続税がゼロになる場合は申告が必要となります。
名義変更について
被相続人の名義だった不動産、有価証券、預貯金などの名義変更をする場合には、有効な遺言書あるいは「遺産分割協議書」、戸籍謄本類、印鑑証明書などの証明書類が必要です。あらかじめ必要書類を確認し、漏れがないようにしましょう。
ご注意(必ずお読みください)
- 当ページは、相続制度の概要等を説明するためのものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。
- 当ページは、当社が信頼できると判断した2016年10月現在の資料・情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証しているものではありません。また、今後の法改正等により内容が変更されることがあります。当ページの利用により当サイトご利用者がいかなる損害を受けた場合であっても、当社はこれに係わる一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 税制に関する税務リスクは、当サイトご利用者自身が負担することになります。具体的な税務上のご質問等につきましては、税理士等の専門家にご相談ください。