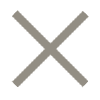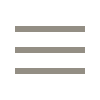ここから本文になります。
出産や育児には、公的な助成や給付などの制度も充実していますが、それでもまとまったお金が必要となります。
ここでは、出産や育児にどのような費用がどのくらいかかるのか見ていきましょう。
出産
出産準備にかかる費用としては、マタニティウェアなどの妊婦用品のほか、妊娠中の健康管理のための運動や子育てのための情報収集の費用なども見ておかなければなりません。つわり等で体調がすぐれない場合には、家事サービスを利用することもあるでしょう。
出産準備に必要なお金の目安
出産準備費用には、妊娠中の検診費用などを計算に入れておかなければなりません。検査費用の基本項目部分に関しては14回まで自治体の助成が受けられます。
しかし、助成金額や助成対象内容については自治体により異なります。おおむね1回の検診につき5,000円~1万円程度の自己負担額が発生することがありますので、5万円~10万円程度の費用がかかると想定しておきましょう。
また、妊娠中は出産後に必要となるベビー用品なども買い揃えておく時期でもありますので、まとまった資金があると安心です。
出産時に必要な費用の目安
出産時に必要となるのは、赤ちゃんを産む際の分娩入院費です。分娩入院費は健康保険の適用外となりますが、健康保険から出産育児一時金として42万円(産科医療補償制度未加入の産院での出産の場合39万円)が給付されますので、実質的な自己負担額は最低数万円程度となります。しかし、個室を利用した際の差額ベッド代や、入院時の食事などの医療外費用は年々増加傾向がみられます。妊婦さんへのサービスを重視した豪華なホテルのような産院も見られるようになり、場合によっては数十万円ほどの自己負担額となってしまうことも珍しくありません。
全国の平均的な出産費用(2019年)
| 入院日数 | 6日 |
|---|---|
| 入院料 | 115,047円 |
| 室料差額 | 18,074円 |
| 分娩料 | 266,470円 |
| 新生児管理保育料 | 49,980円 |
| 検査・薬剤料 | 13,880円 |
| 処置・手当料 | 14,840円 |
| 産科医療補償制度 | 15,740円 |
| 医療外費用(お祝い膳など) | 30,151円 |
| 合計 | 524,182円 |
参考:令和元年 育児一時金の見直しについて(厚生労働省)
育児
小さな子供の育児にかかる費用は、1人当たり年間約100万円と言われています。衣食住や医療費、お祝い行事やレジャーなど、どの程度のお金がかかるのでしょうか?
年間の子育て費用(子ども1人当たり)
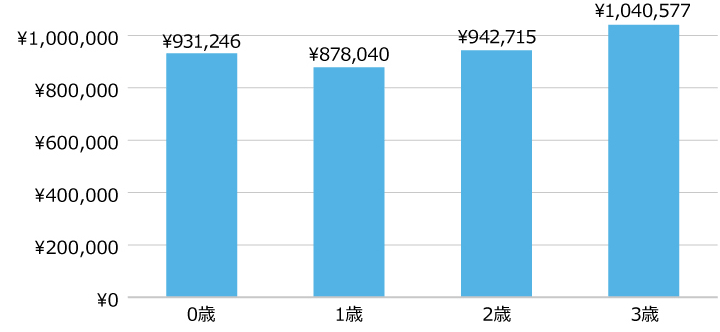
| 衣類・ 服飾雑貨費 |
食費 | 生活 用品費 |
医療費 | お祝い 行事関連費 |
レジャー費 | 子供のための 預貯金・保険 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 88,513円 | 111,128円 | 222,491円 | 12,608円 | 159,354円 | 53,375円 | 221,193円 |
| 1歳 | 69,750円 | 155,376円 | 159,364円 | 14,467円 | 28,314円 | 96,944円 | 223,007円 |
| 2歳 | 65,521円 | 196,849円 | 130,609円 | 10,932円 | 29,514円 | 120,494円 | 195,540円 |
| 3歳 | 62,049円 | 212,782円 | 89,397円 | 11,524円 | 42,734円 | 120,921円 | 188,535円 |
参考: 2009年インターネットによる子育て費用に関する調査報告書(厚生労働省)
衣食住にかかる費用の目安は、年間子育て費用の4~5割程度ですが、0歳時には特に生活用品費が年間平均22万円程度と大きくなっています。これは、おむつなどの消耗品に費用が多くかかるためだと考えられています。子供の成長につれ、衣食住では食費の割合が高くなっていきます。
また、0歳の間は、お祝い行事関連の費用も多くかかることを念頭に入れておきましょう。お七夜にはじまり、お宮参り、お食い初め、初節句など、特にお祝いがたくさんあり、年間費用の平均は15万円以上にものぼります。子供が成長してくるにつれ、レジャー費用も必要になります。0歳時では5万円代ですが、3歳時となると10万円以上が必要となります。
子供の医療費は、自治体の助成がありますので、費用は自己負担で行う予防接種などが主なものとなり、さほど大きな金額はかかりません。しかし、子供が小さなうちに、将来のための預貯金や保険などの金融商品へ支出を行う世帯も多く、その金額は平均年20万円程度となっています。
まとめ
これから出産や子育てを控えている方は、できるだけ早い時期から計画的な資産形成を行っておきたいものです。特に、共働き世帯の場合には、出産前後の収入が減少することも想定し、費用を見積もらなければなりません。預貯金のほか、期間が明確な債券投資や少額から始められる投資信託なども視野に入れておくとよいでしょう。
また、子供のために預貯金を始める方も多いですが、計画的に資金形成を行うには、積立型の商品などが便利です。できるだけ早い段階から預貯金や保険を考えておくと、後の資産形成もスムーズとなるでしょう。