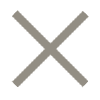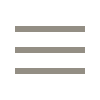ここから本文になります。
退職後の人生設計は立てていらっしゃいますか?現役世代にとっては退職後の生活はイメージしにくいものですが、豊かなセカンドライフを実現するためには、マネープランを早めに立てて計画的に資産を形成することが大切です。
ここでは、退職後の生活に必要な費用について見ていきましょう。
退職・セカンドライフ
現役時代からセカンドライフにシフトした場合、収入が大きく下がることは誰もが予想しているはずです。具体的に収入と支出の変化を見てみると、50~59歳の勤労者世帯の平均収入(賞与を含む)が月収で約69万円のところ、60歳以上年金収入のみになると収入は約24万円と、半分以下に減少します。また、現役世代は、税金や社会保険料の負担が大きいものの、残された手取りから日常の生活費、教育費、住宅ローンなどを差し引いても、貯蓄にまわす余裕があります。ところが、退職後の無職世帯では、税金・社会保障費の負担が少なくなるとはいえ、貯蓄のために残すお金はほとんどありません。
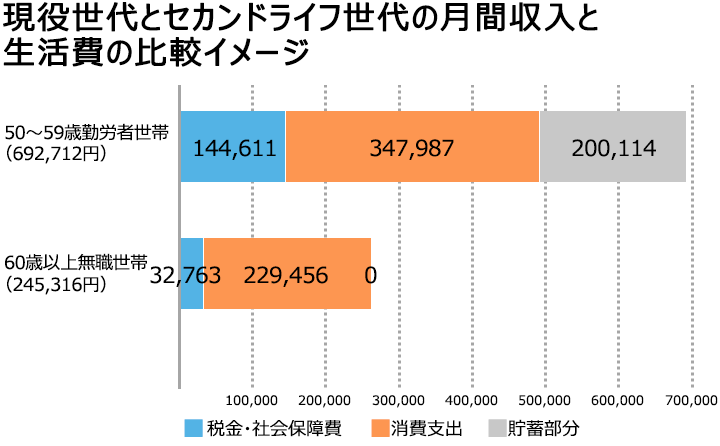
参考:家計調査年報(家計収支編2021年)総務省
セカンドライフにいくら必要?
退職後の生活をイメージするうえで、押さえておきたいポイントは、毎月いくらぐらいの収入があり、生活費はどのくらい必要なのかを把握することです。
以下のデータは、総務省が作成した平均的なシニア夫婦の収入と支出の内訳です。標準的な収入は約23.7万円、支出は約26.0万円、月々のマイナス額は約2.2万円にのぼります。日本人の平均寿命は男性81.47歳、女性87.57歳(「簡易生命表(2022年)」厚生労働省)と、日本は世界有数の長寿国です。65歳以降、セカンドライフ期間が25年と仮定した場合、
- 年金収入(23.7万円×12カ月×25年)7,110万円
- 生活費の支出(26.0万円×12カ月×25年)7,800万円
- マイナス額 ▲690万円
となり、多くのシニア夫婦はマイナス分を退職金や預貯金から補填することになります。
セカンドライフの生活費の内訳
シニア夫婦(夫65歳以上、妻60歳以上)無職世帯の家計収支
| 社会保障給付(公的年金) | 214,530円 |
|---|---|
| その他の収入 | 23,458円 |
| ①実収入 | 237,988円 |
| 食料 | 66,118円 |
| 住居 | 16,425円 |
| 光熱・水道 | 19,563円 |
| 家具・家事用品 | 10,568円 |
| 被服および履物 | 5,147円 |
| 保険医療 | 16,383円 |
| 交通・通信 | 26,909円 |
| 教育 | 7円 |
| 教養娯楽 | 19,831円 |
| その他の消費支出(※) | 47,356円 |
| 税金・社会保険 | 31,789円 |
| 〈②実支出〉 | 260,096円 |
| 〈③収支残(①-②)〉 | -22,108円 |
- …理美容や交際費、仕送り金など
参考:「家計調査 家計収支編(2021年)」総務省
多額の臨時支出に備える
さらに、生命保険文化センターの行なった意識調査(2019年度)によると、ゆとりある老後生活を送るための費用は月36.1万円が必要という結果が出ました。そうなると、月々のマイナス金額は約11.6万円と、大幅な赤字です。
なお、ゆとりのある老後生活に使うお金の使い道とは、旅行・趣味・日常生活の充実・交際費など、家族や友人とよりよい時間を過ごすための資金のこと。「退職後は、のんびり好きなことをして楽しく過ごしたい」と考えているなら、年金収入では不足する金額を早い段階から準備することが大切です。
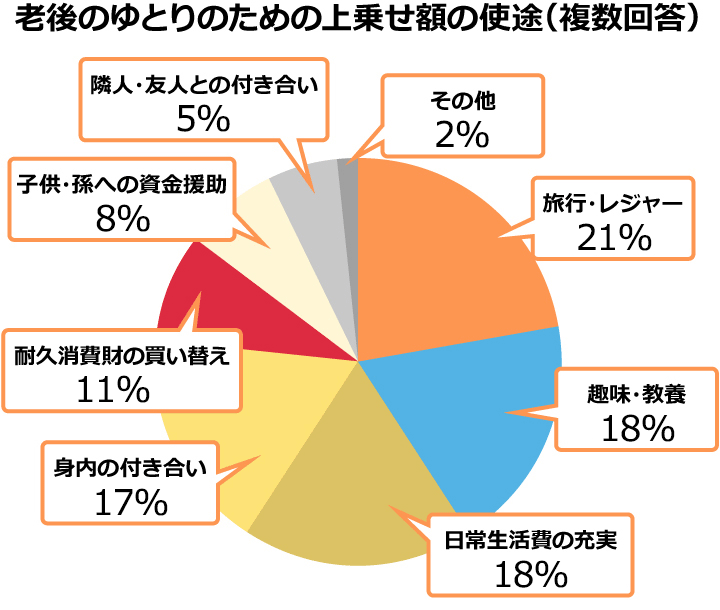
参考:生命保険文化センター「生活保障に関する調査」(2019年)
また、日々の生活費に加えて、イベントごとにもお金がかかります。イベントごとの支出は大きく分けて2種類。税金の支払いやお中元・お歳暮など定期的に発生する予測可能な特別支出と、住宅リフォーム代や冠婚葬祭費用といった不定期に発生する予測不可能な臨時支出です。車を保有していれば、車の買い替え費用や維持費も負担になってくるでしょう。
介護状態になった場合の費用の目安について
そして、老後を考えるうえで目をそらすわけにいかないのが、介護です。介護が必要になる要介護者の割合は、高齢化と共に年々高まっています。厚生労働省の調査によると、介護給付費受給者の割合は65~69歳で男性2.3%/女性1.7%、70~74歳で男性4.3%/女性3.8%、80~84歳で男性15.2%/女性21.7%となっています(参考:「介護給付費実態調査月報」(2020年)厚生労働省)。
要介護状態になったとき、住宅リフォームや介護用ベッドの購入といった一時的な費用の合計は平均74万円、月々の自己負担額は平均8.2万円となっています(参考:「生命保険に関する全国実態調査」(2021年)生命保険文化センター)。
まとめ
セカンドライフでは、日々の生活費を補填する資金、これから使うことが予想される資金、いざというときに使える資金、それぞれのお金を確保することが大切です。
これから退職を迎える方も、すでにセカンドライフを過ごしている方も、将来を見据えて資産を計画的に運用し、老後のお金の不安をなくしましょう。